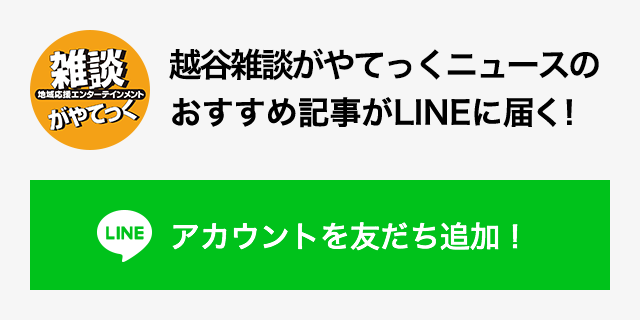<�絶対に甘党宣言!>アイルトン・セナと8050問題【がやてっくグルメ】
- 2022/02/13 06:00
- がやてっく
- がやグルメ

<ブウォーーーン>
<キィーキキ>
<ガシャン>
あと1時間、、、続けようかな。
e-モータースポーツ「グランツーリスモ」が再度再開される。
もちろん隆司は「FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ」に出場できるレベルではない。
そこらへんのe-モータースポーツの大会では上位に入るが、優勝経験はない。
<ブウォーーーン>
<キィーキキ>
<ガシャン>
「今日は調子が悪いな。。。」
感触の悪い音が耳の鼓膜をいやらしく振るわせて静かに萎んでいった。
鼓膜の振動が終わると、必要以上の静けさを感じた。
そう、必要以上の静けさだ。
隆司は時計を見た。
午後8時47分。
午後10時までに南越谷にある倉庫へアルバイトに行かなければならない。
電車で20分ほどかかる。
「よし、そろそろ行くか。」
重い腰を上げた。
その重みは「8050問題」をも含む重みだった。
・
・
・
電車の中で、隆司は久々にアイルトン・セナの事故を思い出した。
あれは、1994年5月、隆司が22歳の頃だった。
当時、埼玉大学の理工学部に通っていた。
単位は誰よりも早く取得し成績も優秀だった。
しかし、「時代」は冷徹に隆司の背中をドロップアウトの穴へと押した。
<ヒューン>
<ドサッ>
<バタン>
大人の欲で膨れたバブルが弾け就職氷河期が始まった直後の年だった。
暗い穴の底から見上げる入口は月のように見えた。
誰かが助けに来たのかもしれない。
いや、誰も気づいていないのかもしれない。
そう、世の中の誰もが自分の存在をすでに忘れてしまったのかもしれない。
<ヒューン>
<ドサッ>
<バタン>
夜になると完璧で完結した闇が訪れた。
隆司は惚れ惚れとした。
いや、惚れ惚れとしなければならなかった。
穴の中で、唯一の変化に心を動かさなければ、本当に存在価値が無くなってしまう気がしたからだ。
<ブウォーーーン>
<キィーキキ>
<ガシャン>
アイルトン・セナは事故で亡くなった。
1994年5月1日、ブラジル国民は全員が涙した。
もちろん、ブラジルのみならず世界中の人々に衝撃を与えた。
「英雄を失った。」
誰もが口々に呟いた。
そして、隆司とは対照的だった。
隆司がポストへ手紙を確認しに行くと不採用通知が投げ込まれていた。
「世界最高のマシーンを作る」というわずかに残った情熱はアイルトン・セナの事故と一緒に心の奥底に葬ったのだ。
「何をしたって俺は3流だ。」
電車は南越谷駅で止まり隆司は席を立った。
立った瞬間に目眩を覚え、駅のベンチに座った。
隆司は予感していた。
開けた目の前に広がる空間は南越谷駅ではなかった。
「僕に期待することはやめてほしい。」
いつもの口癖で出た言葉が「ダンス・トゥ・ザ・ミュージック」のBGMにかき消された。
店員は当たり前のように隆司の机にデザートを差し出した。



隆司は昨日「甘党宣言」をした。
黒いスーツを着た男に指定された場所で宣言をしたのだ。
周りには誰もいなかった。
「俺の予感は当たる。」
隆司は夢中で頬張った。
頬張った白玉が喉に詰まりそうになった。
隆司は50歳となっていた。
当時は、自分が50歳になるとは思っていなかった。
22歳から始まった穴の中の生活が30年近く続くとは思えなかった。
母親は80歳を過ぎ、年金頼りの生活も終わりが近づいていた。
あんみつの甘さは心の鍵を溶かし、閉じ込めていた情熱を露わにした。
「これしきの重さ、どうってことない。」
穴の底で両手を広げると、周りの壁が倒れていった。
月の重力が腰を持ち上げるのを手伝ってくれた。
月のうさぎは知らぬ顔で白玉を作るための餅を搗き続けていた。
・
・
・
隆司はアルバイト先の倉庫の扉に手をかけた。
しかし、そのまま扉を開かずに踵を返した。
「まだまだ勝負はこれからだ。」
隆司は自宅まで走った。
<ブウォーーーン>
<キィーキキ>
<ガシャン>
鼓膜の振動が終わった後の静けさは、今は心地よく感じた。
自宅に到着すると母親の手を握って強く離した。
「俺を誰だと思っているんだ、なぁ、かあさん。」
隆司は情熱が足の指先まで通っていることに少し照れて、それから28年ぶりに笑った。
隆司は真っすぐ前を向き歩を進めた。
新しい「君」と共に。
~END~
※絶対に甘党宣言!の物語はフィクションですが、登場しているデザートは越谷市内の店舗で実際に提供されているデザートです。
※今回は「夢庵 越谷大里店」さんのデザートでした。
-
 【人と人とを工具でつなぐ】2026年1月7日、大里に工具電材買取販売店「リライズ越谷店」がオープンします【がやてっく開店】
【人と人とを工具でつなぐ】2026年1月7日、大里に工具電材買取販売店「リライズ越谷店」がオープンします【がやてっく開店】開店
-
 【工具電材買取店、越谷初上陸!】リライズ越谷店、2025年12月20日にプレオープン!【ジャストコマーシャル】
【工具電材買取店、越谷初上陸!】リライズ越谷店、2025年12月20日にプレオープン!【ジャストコマーシャル】広告
-
 【オープン延期か?!】2025年9月下旬、大里にiクレーン越谷店がオープンします【がやてっく開店】
【オープン延期か?!】2025年9月下旬、大里にiクレーン越谷店がオープンします【がやてっく開店】開店
-
 【電動モビリティを身近に】2025年6月7日、大里にE-WALK Mobility越谷本店がリニューアルオープンしました【がやてっく開店】
【電動モビリティを身近に】2025年6月7日、大里にE-WALK Mobility越谷本店がリニューアルオープンしました【がやてっく開店】開店
-
 【埼玉県初出店ゲームセンター!】2025年8月、大里にiクレーン越谷店がオープンします【がやてっく開店】
【埼玉県初出店ゲームセンター!】2025年8月、大里にiクレーン越谷店がオープンします【がやてっく開店】開店