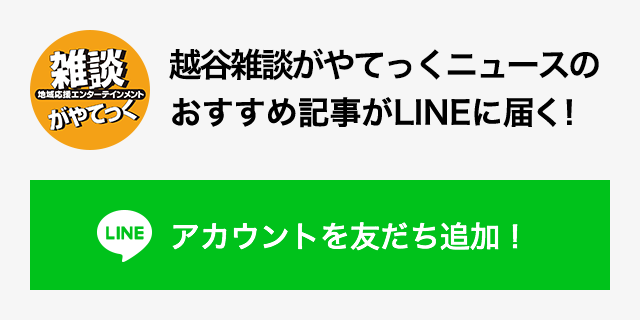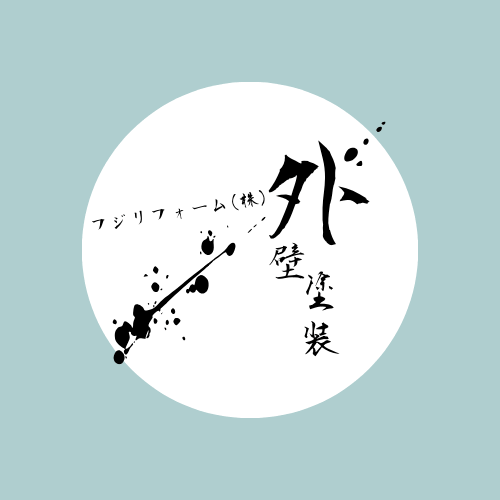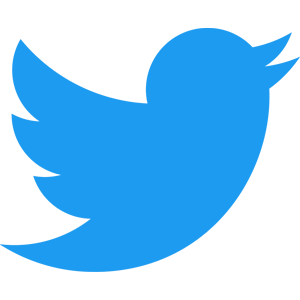「ようかんが食べたい」—シベリア抑留の記憶を越谷から未来へつなぐ【越谷ニュース】
- 2025/08/22 14:11
- がやてっく
- ニュース
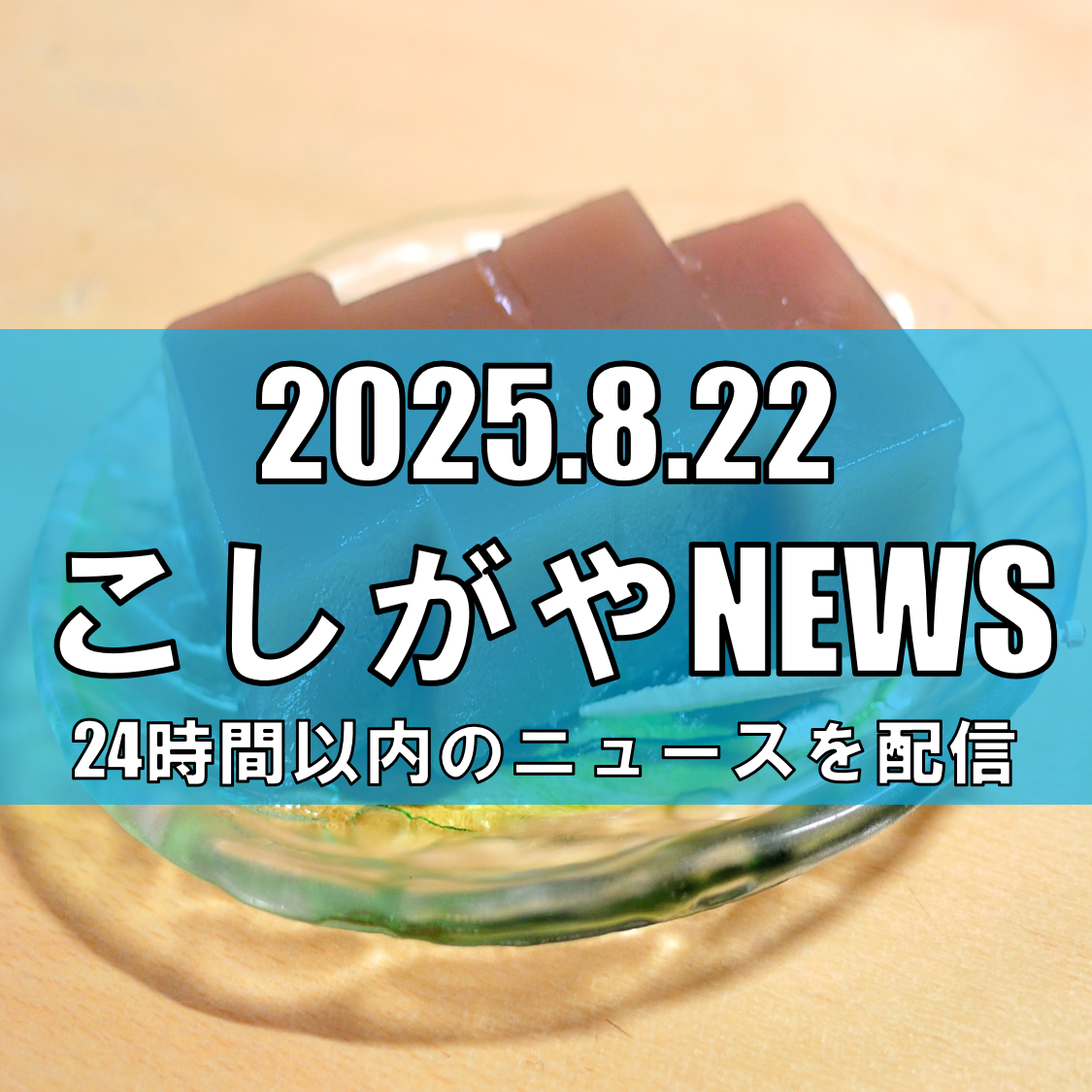
戦後80年、越谷から平和の願いを込めて——シベリア抑留の記憶を語り継ぐ人々
「ようかんが食べたい」とつぶやいた仲間が翌朝亡くなった——そんな過酷な体験を語り継ぐ活動が、埼玉県越谷市で続けられている。全国強制抑留者協会埼玉県支部(越谷市)では、前川佳也支部長(91)、加藤修副支部長(76)、乙訓ますみ事務局長(74)が中心となり、シベリア抑留の歴史を次世代へ伝える取り組みを進めている。
1945年の終戦後、旧満州でソ連軍により連行された日本兵たちは、シベリアやモンゴルの収容所で極寒・空腹・重労働に苦しんだ。厚生労働省の推計では、約57万5千人が抑留され、うち約5万5千人が命を落としたという。
越谷市南越谷地域では、1998年頃から自治会活動を通じて抑留体験者の語り部活動が始まった。きっかけは、故・饗庭秀男さんと故・座間三郎さんの出会い。2人ともシベリア抑留の経験者で、地域活動を通じて知り合い、体験を語り始めた。
座間さんは、満州で武装解除を受けた後、シベリアのコムソモリスクで約2年間の収容所生活を送った。残飯やサケの骨、自分のベルトを煮出して塩分を取るなど、極限状態の中で生き延びた。ようかんを食べたいと願った仲間が亡くなった記憶から、座間さんは生涯ようかんを口にしなかったという。
昨年12月、座間さんは99歳で逝去。現在、体験者不在の中で活動は続いている。今年は初めてさいたま市で展示会を開催し、県内に慰霊碑を建立することを新たな目標に掲げている。
加藤さんは自身の製品開発の経験を活かし、収容所生活を再現するレプリカの製作にも取り組む。前川さん、加藤さん、乙訓さんの3人は「経験者はいなくても、平和を願う地域のボランティアとして、語り継ぐ使命がある」と語る。
越谷から発信される平和のメッセージは、過去の悲劇を忘れず、未来への希望を紡いでいる。